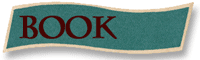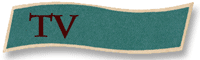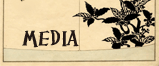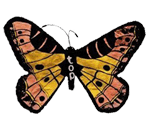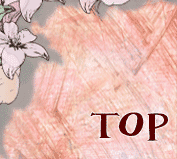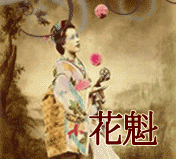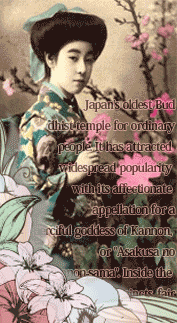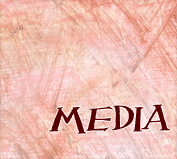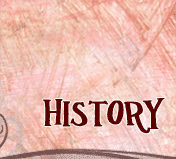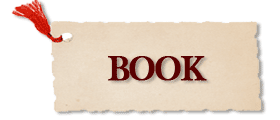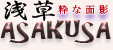浅草オペラの「根岸大歌劇団」の俳優・柳田貞一に弟子入し
1922年(大正11年)3月20日、「根岸大歌劇団」がビゼーのオペラ『カルメン』を初演、
そのコーラスでデビューしている。コーラス・ボーイとして所属し、佐々紅華の創作オペラ『勧進帳』などに出演。
この時代の親友に、後に新劇の名優となり、広島の原爆で落命した丸山定夫がいた。徐々に頭角を現すが、
1923年(大正12年)9月1日の関東大震災によって壊滅的な被害にあった浅草を離れ、当時流行の最先端であった活動写真(映画)
の撮影所がある京都嵐山で喜劇的な寸劇を仲間らと演じていた。この震災前後、エノケンは舞台で猿蟹合戦の猿役を演じたとき、
ハプニングでお櫃からこぼれた米粒を、猿の動きを真似て、愛嬌たっぷりに拾いながら食べるアドリブが観客に受け、
喜劇役者を志すきっかけとなったと言われる。
東亜キネマ京都撮影所、中根龍太郎喜劇プロダクションの端役俳優を経て、1929年(昭和4年)、
古巣浅草に戻り「カジノ・フォーリー」に参加。一度は解散するが、エノケンを中心とした新生カジノ・フォーリーは
、都会的なギャグとコントのセンスで一躍インテリ層の人気を集め、若き文豪であった川端康成が新聞小説『浅草紅団』
(1929年 - 1930年、東京朝日新聞)で紹介。「金曜日の晩には踊り子がズロースを落とす」という噂も手伝って、
連日満員の大入りとなり、浅草の人気者となった。
その後、「プペ・ダンサント」を経て、ジャズシンガーの二村定一と二人座長となった「ピエル・ブリヤント」を旗揚げ。
座付作家に菊谷栄、俳優陣には、中村是好、武智豊子、師匠である柳田貞一らを抱え、これが後に「エノケン一座」となる
榎本 健一(えのもと けんいち)
1904年10月11日~1970年1月7日
は、日本の俳優、歌手、コメディアンである。
当初は浅喜劇王」とも呼ばれ、第二次世界大戦期前後
日本で活躍した。
1925年早稲田大学中退。以降は文筆活動に専念する。雑誌編集の傍ら、宴会での余興芸の延長上で、1926年に親交のあった活動弁士徳川夢声らと「ナヤマシ会」を結成し演芸活動を開始。「声色」と呼ばれていた声の真似芸に「声帯模写」という仰々しい新名称を与え、モダンな芸風が仲間内で好評を博した。
1930年、菊池の後援で『映画時代』の独力での経営に乗り出すが失敗に終わり多額の負債を負う。
雑誌休刊後は東京日日新聞の嘱託として映画・レビューを書いたり、映画関係の書物の執筆、雑誌『漫談』の編集など行ったり
、1931年には五所平之助『若き日の感激』、田中栄三『浪子』などの映画出演を行う。
その後、素人ながら芸達者なところを買われ、菊池寛や小林一三の勧めで喜劇役者に転向[6][7]。
デビューは1932年1月、兵庫県宝塚中劇場公演『世界のメロデイー』だった[7]。このときはロッパのわがままに対する小林の好意で、
フィナーレは花吹雪の中大階段を降りながら歌う演出、千両役者にちなんで千円祝儀にもらうなど破格の待遇をしてもらいながら、
肝心の芝居のほうは本人も恥じ入るほどに散々な出来だった。
そのような失敗を乗り越え、1933年には浅草で夢声・大辻司郎・三益愛子・山野一郎らと劇団「笑の王国」を旗揚げした。
内容は、ロッパの人脈を生かして「ナヤマシ会」関係者や他劇団、映画関係などの寄せ集めで、アチャラカと呼ばれる軽いナンセンス喜劇中心であった。
「前受けばかり狙ったお粗末至極」のものばかりで、ロッパにとっても「思いもかけないことだ!」
と述べているように良家育ちが庶民の街に違和感を覚えるなど苦戦を強いられるが、後に提携を結ぶ脚本家菊田一夫と知の邂逅、
自作の『凸凹放送局』、『われらが忠臣蔵』などの成功で喜劇俳優として成長する。彼自身チャップリンと曾我廼家五郎を崇拝しており
、アチャラカ芝居への理解の深さは、曾我廼家喜劇への造詣から来たもので、喜劇への第一歩も菊池からの「モダン曾我廼家になりたまえ。」
の一言であった
古川 ロッパ(ふるかわ ろっぱ)
1903年8月13日~1961年1月16日
1930年代の日本の代表的コメディアン。
編集者、エッセイストとしても活動した。
俳優、コメディアン、エッセイスト
ジャンル 舞台、映画
浅草の「師匠」
深見はテレビに背を向け、最後まで浅草の舞台で芸人人生を全うした。
深見の舞台はストリップ劇場での、いわゆる「幕間」のコントが主であったが、非常に面白いと評判を呼んだ。
ストリップ劇場であるから客は踊り子の裸目当てに入場しており、コントになると怒号混じりの野次が飛ぶ事も多かった。
深見はそんな客を「うるせぇ、黙って観てろ!」と一喝して黙らせ、何事もなかったようにコントを続行し、
野次を飛ばした客自身も笑わせる事もあったという。
不自由な手でギターなどの楽器を操りタップダンスを踏むなど多芸多才。
アドリブや時事ネタから、場所柄の下ネタまでをも盛り込むコントが持ち味。後にテレビの世界で大活躍する東八郎や萩本欽一なども深見に世話になっていた。
しかしテレビに背を向けた事などで、当時の深見の舞台映像は殆ど残っておらず、「幻の浅草芸人」と呼ばれている。
永年にわたり浅草で生活していたため、シャイで粋を尊ぶ江戸っ子気質を持っていた。
何かにつけて「この馬鹿野郎」と言うなど口は悪かったが、人情家で独特のカリスマ性とリーダーシップがあり人望も厚く、
慕われていた。芸人を引退した時のパーティーには多くの芸人や浅草商店会の人々が駆けつけた。
深見がテレビに背を向けた理由については諸説ある。戦争中に受けた左手の負傷痕を気にした為というものや、舞台芸人である事に誇りを持っていたからというもの、
カメラ位置やスポンサーの意向など何かと制約の多いテレビ番組を嫌ったからというもの等がある。
芸人としての生き方やファッションに独自の美意識を持っており、弟子にも厳しくそれを叩き込み、たけしも非常に影響を受けたと語っている。
以下はその一例。
「芸人は良い服を着ろ。腹は減っていても見えないが、着ている服は見える。特に足元を見られるというように、靴には気を遣え。」
「芸人は外では良いものを食べろ。その金がないなら外へは行くな。」
「笑われるんじゃない笑わせろ。舞台から降りたら格好いいと言われるようにしろ。」
「芸人は芸を持て。楽器でもタップダンスでも良い。ただやるだけではダメだ、舞台で客に見せられるレベルの芸を持て。」
前述のような厳しい指導の一方で、弟子の暮らしぶりには人一倍気を遣い、弟子と一緒に食事する時も自分から酌をしたり、
「あれ飲め、これ食え」と自分の事はそっちのけで世話を焼いた。過度に封建的な師弟関係には批判的で、自分の食事中に弟子に給仕をさせたり外で立たせたりする師匠連中を
「あんなのは田舎者のやる事、楽しむ時は一緒に楽しめばいいんだ。」と語っていた。
たけしは深見からの薫陶と影響を深く受けた。たけしの芸風である毒舌・早口・アドリブなどは全て深見譲りであり、
自分はその心意気を継いでいる。」と語っている。
ある時深見はたけしに「テレビの芸は絶対にこの箱からはみ出せない。まるで芸人の棺桶だ」と言い、興味や出世欲から安易にテレビというメディアに踏み込まないよう釘を刺したという。
深見は漫才を軽演劇より一段下に見ていたようで、たけしが「漫才で勝負したい」と申し出た時も激怒し、破門を言い渡している。ただ漫才云々と言うよりも、
気に入りの弟子が去っていく事の寂しさの方が大きかったと言われている。しかし漫才でメキメキ頭角を現していく姿を喜び、たけしの出演するテレビに見入っていたという。
「まるで実の親子のようだ」と言う人もいた。
たけしが1982年度の日本放送演芸大賞を受賞した際、「小遣いだ」と言って賞金を全て深見に渡した。
深見は馴染みの飲み屋で「タケの野郎がよ、生意気によ、小遣いだなんて言ってよ」と何度も嬉しそうに語っていたという。
失火で亡くなる1ヶ月前の事である。
たけしは『オレたちひょうきん族』収録中、楽屋で深見の訃報を聞いた。
しばし絶句した後たけしは、壁に向かい俯きながら無言でタップを踏み始めた。
生前、深見はたけしに「俺にはお前にも教えていないとっておきの芸がある」と語っていたという。
たけしは幾度となく尋ねたが、深見は頑として答えなかった。
「この芸を見たら、どいつもこいつも驚いてひっくり返る」とまで豪語していたその芸は、深見の死によって永久に謎のままとなってしまった。
たけしは後に「自分は有名になる事では師匠を超えられたが、芸人としては最後まで超えられなかった」と、深見の偉大さを語っている。
深見千三郎(ふかみ せんざぶろう)
(1923年3月31日~1983年2月2日)
北海道浜頓別町出身の舞台芸人、演出家、脚本家。
ビートたけしの師匠。姉は浅草の人気芸者で歌手の「美ち奴」
(みちやっこ)。
何度か結婚しており
最後の妻は同じフランス座の踊り子・紀の川麻里。
ジャンル 舞台、映画